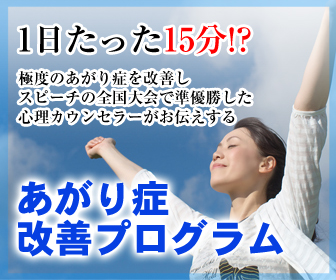あがり症の治し方を知恵袋で探してみた結果面白いことがわかった件
「あがり症の治し方を知恵袋で探しています」
あがり症を克服しようと考えている人の中で、知恵袋サイトを参考にしていたり、自ら知恵袋サイトへ質問を投稿している方が多いようです。
たくさんの方が閲覧している知恵袋サイトでは、回答者の方も多く、
中には有益なアドバイスをくれる方もいます。
そんな、知恵袋サイトを色々と探した中で、面白いことがわかりました。
ということで、この記事では、
あがり症の治し方を知恵袋で探した結果、面白いことがわかったので、それをご紹介していきます。
すでに様々な対策を実践している質問者
あがり症の方の中には、「緊張しない方法」を探している方が多いようで、この質問者も緊張しない方法、緊張を緩和する方法を質問されていました。
ただ、質問者自身ですでにいくつかの対策を行っていたようです。
・腹式呼吸
・顔の体操
・手の付け根のツボ押し
・自分に言い聞かせる
・なるべく低音で話す
ここまで対策されても、緊張が緩和できないようでした。
回答では、
「人前で緊張するのは、自意識過剰ではないか?」
と回答。大勢の前で発表する場面で緊張するのは「自分が注目されている」と思うから緊張するからだ、と回答。
さらにこの回答では、大勢の前で発表する場合、聞いている方は、他人のことなんて特に注目していない。
発表やスピーチを聞きながら、
・今日のデートはどこに行こうかな?
・ランチは何にしようかな
・子どもの誕生日プレゼントは何にしようかな?
こんなことを考えているに違いないので、どうせ聞いていないからリラックスしてスピーチに望めば良い。
と、回答されていました。
この回答を読むと、確かにと納得。
大勢の前で発表した場合、聴衆のすべての人が、発表者やスピーチを行う人に注目しているわけではありません。
中には真剣に聞いている方もいるでしょう。
しかし、あなたが全身全霊を込めて作ったプレゼン資料も、スピーチの原稿も、
聴衆の中には、聞きながら全く別のことを考えている方がいます。
・・・というか、真剣に聞いているふりをしながら、「今日の晩ごはんは何を食べようかな・・・」とか、考えている方のほうが多いかもしれません。
「どうせ聞いていないんだから、気軽にやろうか・・・」
と考えるのも、一つの手段でしょう。
「要は慣れ」という回答が意外と多い
あがり症の方が、自分の症状を改善したくて質問している「知恵袋」の中で、一番多い回答が「要は慣れ」です。
・場数を踏む
・発表の場に慣れる
など、たくさんの人の前に立つという経験を沢山積むことで、緊張度が無くなる、もしくは緊張の度合いが少なくなると回答している方がほとんどです。
それでも、質問者の方が減らないのは、経験しても緊張してしまうという方が多いか、「経験が少ない」かの、どちらかでしょう。
回答者の中で、なぜ「慣れ」が一番多い回答なのかというと、自身の経験からいうと、場に慣れると緊張が緩和されていくと経験した方が多いからです。
発表やスピーチの場で場数を踏み、慣れていくと、緊張の度合いも緩和されていきます。
場数を踏むということは、発表やスピーチをすることに慣れていくと、周りを見る余裕ができるからです。
発表やスピーチをしながら周りを見る余裕ができてくると、誰も自分の話を聞いていないことに気づき、
「聞いている人が少ないから、リラックスして話すか・・・」
と、心の余裕もできます。
場数を踏むと緊張が少なくなるのは、そういった理由からなのです。
たまにアフィリサイトへの誘導をしている回答者
回答者の中には、自分のアフィリサイトへ誘導してくる方もいます。
有益な情報が記載されているのであれば、アフィリサイトでも気にせずに大いに利用、参考にすれば良いと思いますが、
「アドバイスする気がなくて、完全に誘導目的だな・・・」という方も中にはいます。
そういう方には、少し注意したほうが良いでしょう。
また、アフィリサイトへの誘導目的で、質問者も回答者も自作自演で、アフィリサイトへの誘導を行っている方もいるようです。
ただ、そういう場合は、質問の内容も、回答の内容も、内容が薄く、ちょっと違和感を感じますので、
「自作自演ぽいな・・・」と感じたら、あまり参考にする必要はないでしょう。
”アフィリサイト”でも、しっかりと情報を調査して掲載しているサイトが多いので、有益な情報であれば、参考にしてもよいでしょうが、
自作自演で誘導されているようなサイトは、内容が薄い場合が多いので、少し注意が必要ですね。
まとめ
この記事では、
あがり症の治し方を知恵袋で探した結果、面白いことがわかったので、それをご紹介していきました。
知恵袋サイトでは、有益な情報も、ためにならない情報もありますし、他のサイトへの誘導目的の回答もあります。
それらを厳選して、「これだ!」と思える質問、回答の出会えたら、自身の参考にしてみるのもいいでしょう。
過去に誰かが経験したような回答であれば、なおさら参考になるので、しっかりと活用していきたいですね。